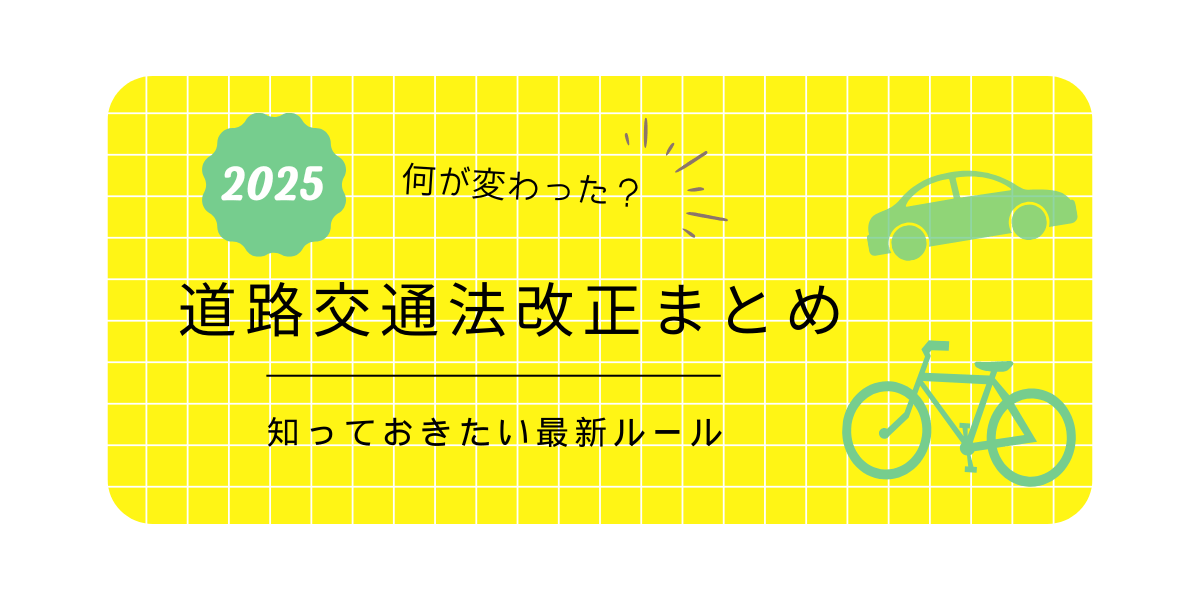2025年、道路交通法に大きな改正がありました。
免許制度の利便性アップから、自転車ルールの厳格化、自動運転社会への準備まで、私たちの日常に影響する内容が盛り込まれています。
この記事では、2025年から施行された道路交通法の変更点と今後予定されている改正をわかりやすく解説します。
2025年の改正は「免許制度の利便性向上」「自転車関連のルール強化」「自動運転社会への準備」です。
1.2025年道路交通法の主な改正ポイント一覧
- マイナンバーカードと運転免許証の一体化
- 原付バイクの定義変更(125cc以下・出力4kW以下が対象に)
- AT限定解除教習の短縮化
- 自動運転(レベル4)に対応する新ルール
- 遠隔操作型小型車の通行規定
- 自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」禁止(2024年末施行済み)
- 自転車違反に反則金(青切符)制度導入(2026年予定)

2.参考リンク
・警察庁|道路交通法の改正
・JAF|交通安全と道路交通法改正
・政府広報オンライン
3. 免許制度の変更
2025年3月から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化がスタートしました。
これにより、お財布の中でカードが増える不便さが解消されると期待されています。また、AT限定免許からMT免許への切り替え(限定解除教習)の時間が短縮され、より効率的に取得できるようになります。
4. バイク・原付に関する改正
2025年4月からは、原付の定義が変更されました。これまで50cc以下だった「原付一種」に、排気量125cc以下・出力4kW以下のバイクも含まれるようになります。若年層や日常利用者にとって選択肢が広がる一方、運転区分やルールをしっかり理解しておく必要があります。
5. 自動運転と遠隔操作型小型車の新ルール
自動運転技術の進化を受け、2025年からレベル4相当の「特定自動運行」に関するルールが施行されました。事業者は国の許可を受けて運行でき、将来的には無人バスや配送ロボットの実用化が進むと考えられます。また、遠隔操作によって小型車を走行させるための定義や届出義務も明確化されました。
6. 自転車に関するルール強化
近年増えている自転車事故への対策として、
- 「ながらスマホ」の禁止
- 酒気帯び運転の罰則化
- 重大違反者に対する講習制度
が導入されました。さらに2026年からは、自転車違反にも反則金制度(青切符)が適用される予定です。
7. 今後予定されている変更
2026年以降も道路交通法の見直しが予定されています。
例えば、生活道路(幅員5.5m以下)の法定速度が30km/hに引き下げられるほか、自動車が自転車を追い越す際の安全間隔ルールも追加される見込みです。
8.2026年自転車で違反すると罰金を支払うことになる
2026年4月1日から施行される改正道路交通法で、16歳以上の自転車運転者の交通違反に「青切符」による反則金が導入されます。
主な違反と罰金額は以下の通りです。
| 違反行為 | 反則金額(青切符) | 備考 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用など | 12,000円 | ながらスマホ 画面注視や通話を含む |
| 信号無視 | 6,000円 | 赤信号や横断歩道以外での横断など |
| 通行区分違反 | 6,000円 | 歩道の標識なしでの通行、車道逆走など |
| 並進禁止違反 | 3,000円 | 横に並んで走行(2台以上横並び走行) |
| 乗車積載制限違反 | 3,000円 | 2人乗りなど |
| 制動装置不良 | 5,000円 | ブレーキが効かない状態での運転 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 | 傘差し運転、音が聞こえないイヤホン利用 |
| 夜間無灯火 | 5,000円 | ライト未点灯 |
| 駐停車違反 | 9,000円 | 車道や歩道上への駐輪等 |
| 一時不停止 | 5,000円 | 一時停止標識で止まらない |
さらに重い違反(酒酔い運転・妨害運転等)は、赤切符となり、刑事罰(懲役・罰金刑、前科)になる場合があります。16歳未満は対象外ですが交通ルールを守り安全に運転することを心がけましょう。
青切符とは
比較的軽い交通違反をした時に警察が渡す「交通反則告知書」(青い紙)のことで、この青切符を受け取ると反則金を支払うことになります。支払うと刑事罰(裁判や前科)が科されません。
16歳以上の二人乗りと13歳未満の自転車ルール
13歳未満の子どもは安全のため歩道通行が認められています。ヘルメットの着用は努力義務です。
16歳以上の運転者が「幼児用座席」や「幼児2人同乗基準適合自転車」で幼児を乗せるなどの決められた構造や条件を満たした場合のみ例外が認められています。
9. まとめ
2025年の道路交通法改正は、私たちの生活に直結する大きな変化です。
特に免許制度や自転車ルール、自動運転に関する部分は日常的に関わる可能性が高いので覚えましょう。
今後も改正は続くため、最新情報をキャッチして安全運転に!